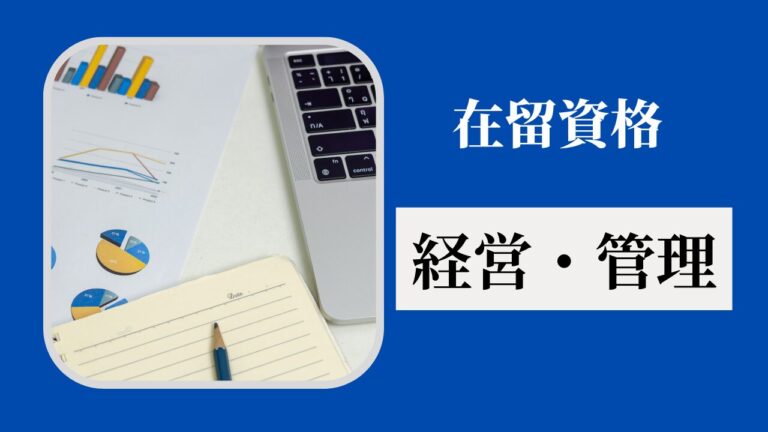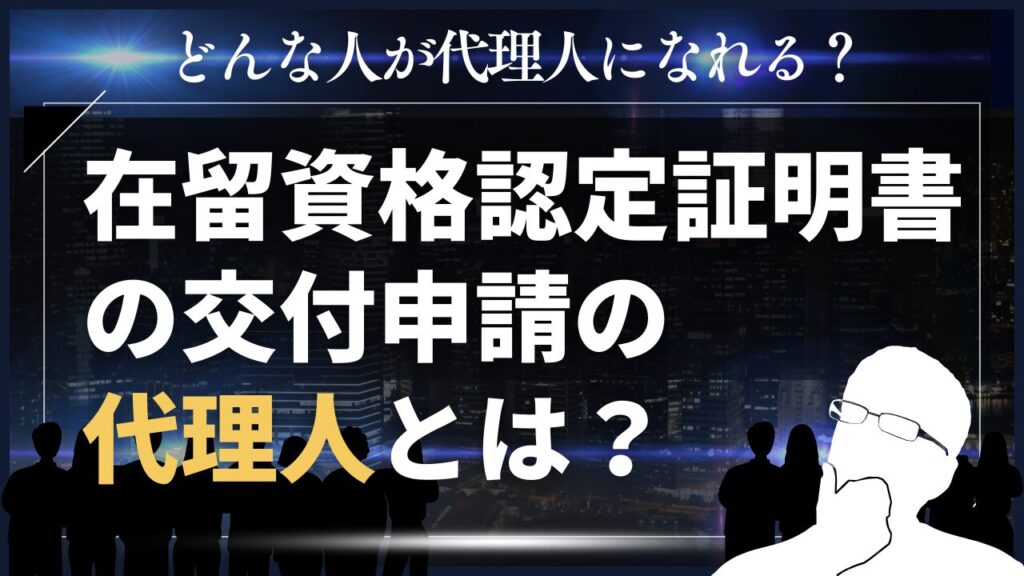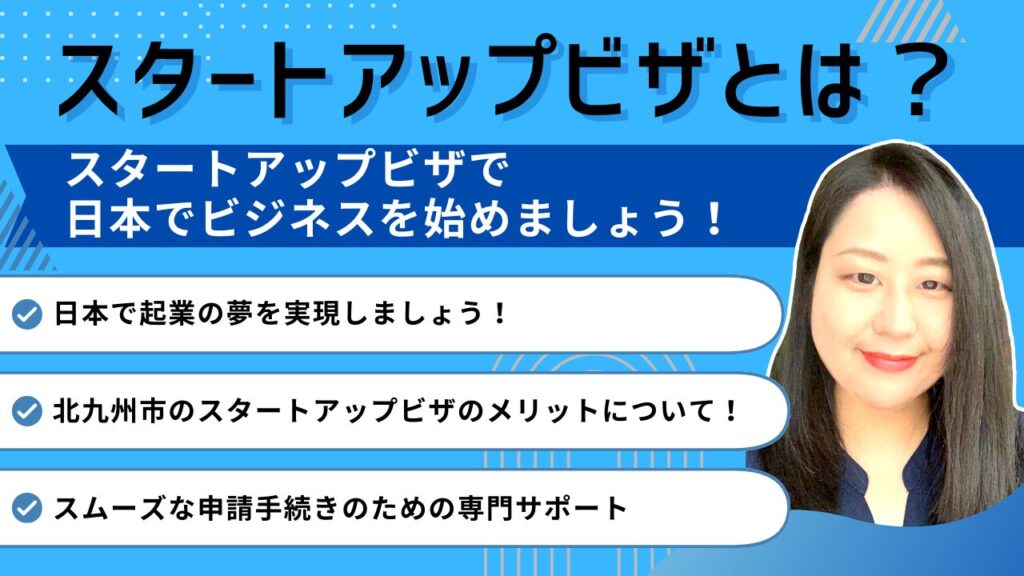外国人は、原則として在留資格を持っていないと、日本に在留することはできません。
その外国人が日本で行おうとする活動が、法務省の定める在留資格に該当しなければ、在留資格を与えられることはありません。
▷在留資格と査証の違いについてはこちらの記事でまとめています。
在留資格は、さまざまなものがあります。
日本で会社経営するために必要な在留資格は「経営・管理」です。
今回は、この「経営・管理」という在留資格について紹介します。
Some of our older articles may still mention the ¥5 million capital requirement and other outdated criteria.
Please note that as of October 16, 2025, Japan’s Business Manager Visa standards have been significantly revised —
now requiring ¥30 million in capital, at least one full-time employee, and B2-level Japanese ability (JLPT N2), among other updates.We are gradually updating all related articles to reflect these new standards.
For the latest and most accurate information, please refer to the article below 👇
👉 Business Manager Visa Reform 2025 – New Requirements and Key Changes
在留資格は大きく2系統
在留資格は在留の目的に応じて大きく2系統にわかれます。

日本で行う活動に応じた在留資格
例)就労・留学・家族滞在など
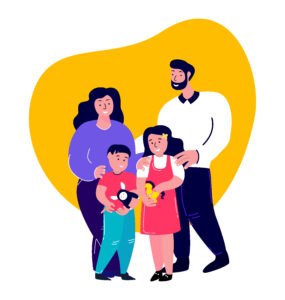
身分や地位に応じた在留資格
例)永住者・日本人の配偶者や子など
参考:在留資格について(出入国在留管理庁のページです)
中長期在留者とは?~在留資格を与えられる外国人~
入管法第19条の3には、以下のように書かれています。
入管法第19条の3(中長期在留者)
出入国在留管理庁長官は、本邦に在留資格をもって在留する外国人のうち、次に掲げる者以外の者(以下「中長期在留者」という。)に対し、在留カードを交付するものとする。1号:3月以下の在留期間が決定された者
2号:短期滞在の在留資格が決定された者
3号:外交又は公用の在留資格が決定された者
4号:前3号に準ずる者として法務省令【施行規則19条の5】で定めるもの
つまり、中長期在留者とは・・・
・3か月以上日本に在留する
・「短期滞在」「外交」「公用」の在留資格が与えられていない
・「特定活動」の在留資格が決定された台湾日本関係協会の日本の事務所、若しくは、駐日パレスチナ総代表部の職員又はその家族ではない
・特別永住者ではない
在留資格は29種類(令和6年8月時点)
法務省が定めている在留資格は29種類あります。
今回は、そのうちの「経営・管理」について紹介します。

※本ページの内容は、2025年時点の制度・審査運用を前提として作成した解説記事です。
法令改正や入管実務の運用変更により、現在の取扱いと異なる場合があります。
現在、内容の更新・見直し作業を進めておりますので、最新の制度内容については出入国在留管理庁の公式情報をご確認ください。
在留資格「経営管理」
日本で事業の経営を行い、又は事業の管理(幹部等)に従事する活動を目的とする外国人に与えられる在留資格。単に会社を設立するだけでは認められず、設立した会社の事業についての安定性・継続性を事業計画書等で立証していく必要があります。業種や業態については特に制限はありませんが、麻薬の売買や賭博などの法令上適正に営まれていない事業の経営・管理の場合はもちろん該当しません。
・該当例
入管法別表第一によると・・・
本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。)
つまり、以下の者が該当します。
企業等の経営者・管理者
・在留期間
5年、3年、1年、6月、4月、3月
・経営者・管理者とは?
①経営者とは?
日本国内に事業所を有する法人の経営者のことです。この「経営者」とは、会社の重要事項決定権や業務執行権などを有している実質的な役員(代表取締役・取締役等)のことです。会社の重要事項決定権や業務執行権などを有していない形式的な役員の場合は、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得することになります。
出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(令和7年10月16日改正施行)によると・・・
【法別表第一の二の表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動】
申請人が次のいずれにも該当していること。
一 申請に係る事業を営むための事業所が本邦に存在すること。ただし、当該事業が開始されていない場合にあっては、当該事業を営むための事業所として使用する施設が本邦に確保されていること。二 申請に係る事業の規模が次のいずれにも該当していること。
イ その経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する常勤の職員(法別表第一の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)が従事して営まれるものであること。
ロ 申請に係る事業の用に供される財産の総額(資本金の額及び出資の総額を含む。)が三千万円以上であること。三 申請に係る事業の経営を行い、又は当該事業に従事する者(非常勤の者を除く。)のうちいずれかの者が、高度に自立して日本語を理解し、使用することができる水準以上の能力を有している者であって、かつ、申請人が当該事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する時において、本邦に居住することとしているものであること。
四 次のいずれかに該当していること。
イ 経営管理に関する分野又は申請に係る事業の業務に必要な技術若しくは知識に係る分野において博士の学位、修士の学位又は専門職学位(学位規則(昭和28年文部省令第9号)第5条の2に規定する専門職学位をいい、外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有していること。
ロ 事業の経営又は管理について3年以上の経験(特定活動の在留資格(法第7条第1項第2号の告示で定める活動のうち本邦において貿易その他の事業の経営を開始するために必要な事業所の確保その他の準備行為を行う活動を含む活動を指定されたものに限る。)をもって本邦に在留していた期間がある場合には、当該期間を含む。)を有していること。三 申請人が事業の管理に従事しようとする場合は、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
経営・管理ビザ(最新版:2025年10月16日施行)要件と実務ポイント
1. 改正後の許可基準(要点まとめ)
新基準は「実体ある経営」を強く求めます。旧来の「500万円 or 従業員2名」ではなく、以下が必須・新設になりました。
常勤職員の雇用(1名以上)—必須
-
対象は日本人・特別永住者・法別表第二の在留資格(「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」)。
-
申請者本人は“常勤職員”に含められません。
資本金の額等:3,000万円以上—必須
-
法人:株式会社=払込済資本金、合同/合名/合資会社=出資総額。
-
個人:事業所確保、1年分の給与、設備投資等、事業のために実際に投下された総額で判定。
日本語能力:B2相当以上(JLPT N2等)—申請者または常勤職員のどちらか
-
JLPT N2、BJT400点以上、日本の高等教育卒・義務教育修了+高卒、在留20年以上 などで立証可。
-
日本語能力の“常勤職員”には、法別表第一の在留資格(例:技術・人文知識・国際業務)も含まれます。
-
ただし、雇用要件の“常勤職員”は上記(1)のとおり法別表二等に限定されます。ここが最大の注意点。
学歴・職歴要件(いずれか)—新設/明確化
-
関連分野の博士/修士/専門職(外国の同等学位を含む)、または
-
事業の経営または管理について3年以上の経験(※起業準備の特定活動期間も算入)。
事業計画書の“専門家確認”の義務化—新設
-
中小企業診断士・公認会計士・税理士が、具体性/合理性/実現可能性を確認。
-
なお、弁護士・行政書士以外が、官公署提出書類を報酬を得て業として作成するのは行政書士法違反のおそれ。役割分担に注意。
事業所の要件の厳格化
-
規模に見合う独立した事業所が必要。自宅兼事務所は原則不可。バーチャルオフィス等も不可。
公租公課の履行確認(更新時)
-
労働保険(雇用/労災)、社会保険(健保/厚年)、国税・地方税の加入・納付状況を確認。
許認可が必要な業種の扱い
-
在留許可後でないと取得できない場合は理由書を提出し、次回更新時に取得状況を確認。
在留中の長期出国
-
正当な理由のない長期不在は活動実態なしとみなされ更新不許可のリスク。
※経過措置:施行日から3年(~2028/10/16)の間の更新は、新基準未達でも経営状況や見込み等を踏まえ総合判断(専門家評価文書の提出を求められる場合あり)。2028/10/17以降の更新は新基準適合が原則必須。
また、**特定活動(44号・スタートアップビザ/51号・起業準備)→「経営・管理」**の切替は、告示や申請日の前後で適用基準が変わります(最新運用に合わせて個別確認を)。
2. 「管理者」とは?
管理者とは、日本国内の事業所における事業運営を管理する者のこと。役職名(例:工場長)だけでは判断されず、実際の職務内容で見られます。
立証のための代表的資料:
-
経営または管理に関する3年以上の経験を示す書類
-
日本で行う事業に関連する職務に従事した期間の証明
-
職務内容・期間が明示された履歴書 等
3. 他の在留資格との関係(経営可否)
-
活動制限のない在留資格(永住者/日本人の配偶者等/永住者の配偶者等/定住者)は、在留資格のまま経営可。
-
「経営・管理」以外の一般就労系(例:技人国 等)は、そのまま会社経営は不可(在留資格変更が必要)。
-
高度専門職:1号ハ・2号は枠組みにより対応可(1号イ・ロは限定的に可能な場合あり/実務は個別確認)。
4. 「経営・管理」の活動範囲(例)
-
新たに事業の経営を開始/その管理に従事
-
日本で既に営まれている事業に参画して経営・管理に従事
-
既存の経営者に代わって経営・管理する活動
5. 取得に向けた実務フロー(準備~申請)
(1) 会社設立準備
独立した事業所の確保(必須)
-
日本国内に事業所を確保。自宅兼用・バーチャルオフィスは原則不可。
-
電話・複合機・什器、店舗なら内装・メニュー等、即営業可能な状態が望ましい。
銀行口座の開設(資本金払込)
-
設立時は発起人等の日本国内の銀行口座に資本金を払込。
-
単独設立で海外在住者の場合、短期在留→口座開設の実務ハードルがあるため、在留資格や銀行要件の確認が必要(6か月以上在留を求める銀行もあり)。
(2) 事業規模の立証(新基準に更新)
-
資本金等3,000万円以上(法人=登記事項証明、個人=投下総額の契約書・領収・送金記録等)。
-
常勤職員1名以上の雇用(日本人・特永・法別表二)。雇用契約・社保加入で実体を示す。
-
日本語B2(JLPT N2等):申請者または常勤職員のどちらか。
-
※日本語要件の“常勤職員”は法別表一でも可(例:技術・人文知識・国際業務)。
-
申請書には「誰が」「どの基準で」満たすかを具体的に記載。
-
(3) 事業計画書(専門家確認が義務化)
-
中小企業診断士/公認会計士/税理士の確認書を添付。
-
A4で7~10枚程度を目安に、収益モデル・市場・集客・人員計画・資金繰り・損益計画まで整合的に。
(4) 許認可・届出
-
業種ごとの営業許可(例:飲食=食品営業許可、酒販=酒類販売業免許、古物商 等)
-
税務署・年金事務所・ハローワーク 等の各種手続を適切に。
6. 経営者の経験(評価のされ方)
学歴(修士以上)または3年以上の経営管理経験のいずれかが新基準で求められます。
経験が乏しい場合は、役員構成やアドバイザー体制/専門家確認/計画の合理性で補強を。事業計画書で客観的に黒字化までの道筋を示すことが重要です。
7. 不許可・減点につながりやすい例(最新版)
-
事業所が不適切(自宅兼・バーチャル・用途が「居住用」の賃貸 等)
-
資本金等3,000万円の立証が不十分、常勤職員の在留区分が要件外
-
日本語B2の立証不足(誰が・どの基準で満たすか不明)
-
専門家確認のない/内容が粗い事業計画書
-
労保・社保・税の未加入/未納
-
実態の乏しい委託中心で、経営者としての実体が認められない
-
長期出国で活動実態なしと判断されるおそれ

8. まとめ
-
新基準は雇用+資本+日本語+学歴/経験+専門家確認+適正な事業所まで総合的に実体を求める内容です。
-
更新までの3年間は移行措置があるものの、最終的には新基準適合が前提。
-
これから申請・更新される方は、早めの体制整備と証拠資料の整理、そして専門家との連携が成功の近道です。
関連記事
さいごに
今回は、在留資格の「経営・管理」について紹介しました。
在留資格「経営・管理」は、日本でビジネスをはじめたいと思う外国人の方に必要な資格です。そして、この「経営・管理」の在留資格は、他の資格に比べて取得が難しいとされています。実現性のある事業計画書を作成して、安定して継続できる事業だということを客観的に証明しなければなりません。また、会社設立後に在留資格の取得という流れとなるため、5か月程は時間を要する場合が多いです。専門家に相談して、時間に余裕を持って準備しましょう。当事務所では、経営管理ビザ取得のサポートをしております・どうぞお気軽にご相談ください。
外交・公用
教授
芸術
宗教
報道
高度専門職
法律・会計業務
医療
研究
教育
技術・人文知識・国際業務
企業内転勤
介護
興行
技能
特定技能
技能実習
文化活動
短期滞在
留学
研修
家族滞在
特定活動
永住者
日本人の配偶者等
永住者の配偶者等
定住者
Contact
当事務所では、オンライン面談や出張相談にも対応しております。営業日ではない日も、できるだけメールやLINEのお問い合わせは対応いたしますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。